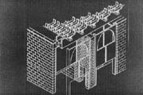アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


アメリカからヨーロッパでの修業を経て日本に帰ってきて最初に「九州芸術工科大学」の新しいキャンパスを設計しました。
キャンパスの配置は大学のアカデミックプランを考慮しながらやりましたから、それなりにひとつの解答になっているといまでも思っていますが、問題は壁なんです。まあ、反省の意味も含めてお見せしますが、この壁はいかにも重いんです。重いというのは感覚的なことだけじゃなくて、空間に対応するいろいろな壁があるべきなのに、この建物ではまだあまりありません。若干上のほうから光を入れたり、覗き窓をつくったりしてはいますけれど、もっと生き生きとした対応ができるはずなのにできていません。完成してからつくづくそう思いました。恥ずかし気もなく、カーンのところで勉強したやり方を使ってはいますが、特に広場を囲むスペースなどに、もう少し生き生きとした対応が可能だったと思います。空間の文節、たとえば人間の溜まる場所、あるいはひとつひとつの小さな部屋といった構成はまあうまくできていると思います。
それから数年後に、また大学の設計を頼まれました。「相模女子大学」です。この大学はちょうどその一八年前に、私が担当して一号館というのを設計したものなんです。今回は大小の教室、ラウンジなどからなる七号館ということで、設計が先ほどの山荘をやっていたのと同じ時期だったので、住宅と違ったスケールで同じことを考えてやったものです。つまり、建物の前に大きな並木道と広場があるのですが、それに対応するにふさわしいスケールのガラスブロックのスクリーンを立てています。機能的にはこのスクリーンで強い西日を遮っています。しかし、基本的には建物前面の広場に対応するスケールを作り出すことが目的のスクリーンなんです。建物と広場との間にもうひとつのゾーンをつくる。別な言葉でいえば、複数の壁で空間を仕切るということです。そうしたことを考え始めた最初の作品です。
並木道の反対側には一九六五年完成の一号館が建っています。七号館はこれと直交しています。一階の列柱とその上にのるスクリーンということで、スクリーンは立っているだけじゃなく、逆に凹んだところなどもあって、そこが小さな広場になっています。七号館は一九八一年に完成しています。 相模女子大学では引き続き図書館と研究棟を設計しまして、目下、工事にかかっております。それでようやくキャンパスらしく囲まれた広場を完成できるわけです。二五年近くかかっていまようやくこれができようとしています。こうなってきますと、ますます私がいままで申し上げたこと、すなわちさまざまな壁が複数立つという意味が問われます。いろいろな形の切り方、囲み方をさらに発展させていこうと考えております。
これも、実は原形はカーンの有名なプロジェクトにあります。アフリカのルワンダのアメリカ領事館の計画で、実際には建てられませんでした。カーンはこの建物で大きな開口部を彼のいう廃墟の壁で覆ってしまったんです。ちょうどローマの廃墟にあるような壁を立てています。暑い光を遮り、なおかつ見せたいところは見せるという考え方です。
ここでは屋根もそういう考えで設計しています。屋根は防水をして雨を防ぐためのものですが、赤道直下では特に暑い日射を遮るというのも大事な役目です。古くから原住民は土の屋根の上に草の屋根をのせてそれを解決してきました。すなわち、雨を防ぐ屋根の上に日射を防ぐ屋根をのせているんです。カーンはそれを採用したんです。私たちも屋根なら単純に屋根と考えがちですが、屋根の意味ひとつ取り上げても実に複雑なんです。このプロジェクトは、それを造形的に分解してつくるということを試みたものです。
実はこうしたことについても、歴史的な建物を見ますと、たとえば小堀遠州の孤蓬庵はいいなぁという風に思いますが、やはりそれだけで終わるのは素人だと思います。修学旅行などで見学した人たちにとっては「ベニスの建物はきれいねぇ、レース細工みたいですてきだわぁ」でいいですが、私たち建築家はそこからもう一歩踏み込まなくてはいけない。一体、これはなぜ面白いのか、きれいなのか、何が他にない何かを生み出しているのかということを考えなくてはいけないんです。
そこでひとつの鍵はいうまでもいなく、常に私たちが当たり前に思っていることが、独特に組み替えられているということですね。小堀遠州がやった有名なことは、障子の下を開けるという、それだけのことですけれど、彼がやったのは、その障子というもの、すなわち壁というものをもう一度組み直しているわけです。
ベニスの建物が独特なのは、結局のところ運河や広場から反射してくる光を下から建物に入れている点です。日本の建物の特徴のひとつも実はそこにあります。すなわち、上からくる直射日光はできるだけ淡くさせ、光はむしろ下のほうから入ってこさせる。
これが小堀遠州の不思議な開口部が持っている形の面白さと、私たちに与える意味の面白さです。そういう例で見ますと、いろいろな建物からいろいろな例が見えてきます。
ひとつ例を挙げますと、十九世紀のアメリカで流行ったひとつのスタイルで、スティックスタイルというのがあります。歴史家はこの様式とゴシック様式の関連などを云々しますが、私たちは設計者としてどこが面白いかということを見ればいいんですね。たとえばこれはH・H・リチャードソンが建てた住宅の例ですが、建物の外側をもう一度壁が取り囲んでいるんですね。中世ヨーロッパの木造住宅に見られる手法の新しい応用です。ですから、その室内は建物本体が色ガラスで囲まれているために、その間が不思議な光で満たされています。この雰囲気は形は違いますし、全く同じというわけではありませんが、先ほどの日本的な空間に共通なものといえます。
このように、壁は壁、開口部は開口部といっても、実は非常にさまざまな形をとって世の中に存在しているということがわかります。
次は「千駄木の町家」として発表したものですが、自邸です。ここでもう一度自分なりにいろいろ組み直してつくってみました。東京の千駄木というところは、昔、森鴎外や夏目漱石も住んでいたという、本郷のいちばん古い住宅地で、私の家の周囲はたまたまそうした古い雰囲気がよく残っている一角なんです。そこにあった古い町家を取り壊し、鉄骨造で容積いっぱいの三階建ての住まいを建てました。
道に面してのファサードをつくり、なおかつ周囲の家の視線を遮ったり、必要な光を入れたりするためのいろいろな意味を持たせたガラスブロックのスクリーンを立てました。 一階はポーチと露地庭になっており、その前に道路の溝の蓋として用いられるグレーチングを利用した大きな鉄格子を入れ、ガラガラッと開けます。基本的には九〇〇角のグレーチングをいくつか組み合わせてステンレスのボルトで締めているだけのものです。
これは、台湾に近い沖縄の南の島に建つ住宅です。ここは非常に平坦な島で、そのゆるやかな丘の頂上に立っています。台風の通り道で、風速何十メートルというのが何度もやってきます。そして日差しが非常に強い。ですから、沖縄の民家の伝統的な手法である、石垣で囲むという方法がいちばんここにはふさわしいんです。しかし、私はコンクリートのフレームをつくり、その中にすっぽりと木造の住宅を入れてしまうという手法をとりました。フレームを強固にするために非常に太いチークでつくったスクリーンを嵌め込んでおります。この住宅は千駄木の自邸とは違って、非常に広い敷地にフリースタンディングの状態で立っています。そこに開けたり閉めたり日差しを遮ったりするものをいろいろ嵌めていったということです。
以上は壁、それからそこに開ける開口部といったことについて、自分なりにいろいろ組み直したりしてきた実例を挙げてみました。